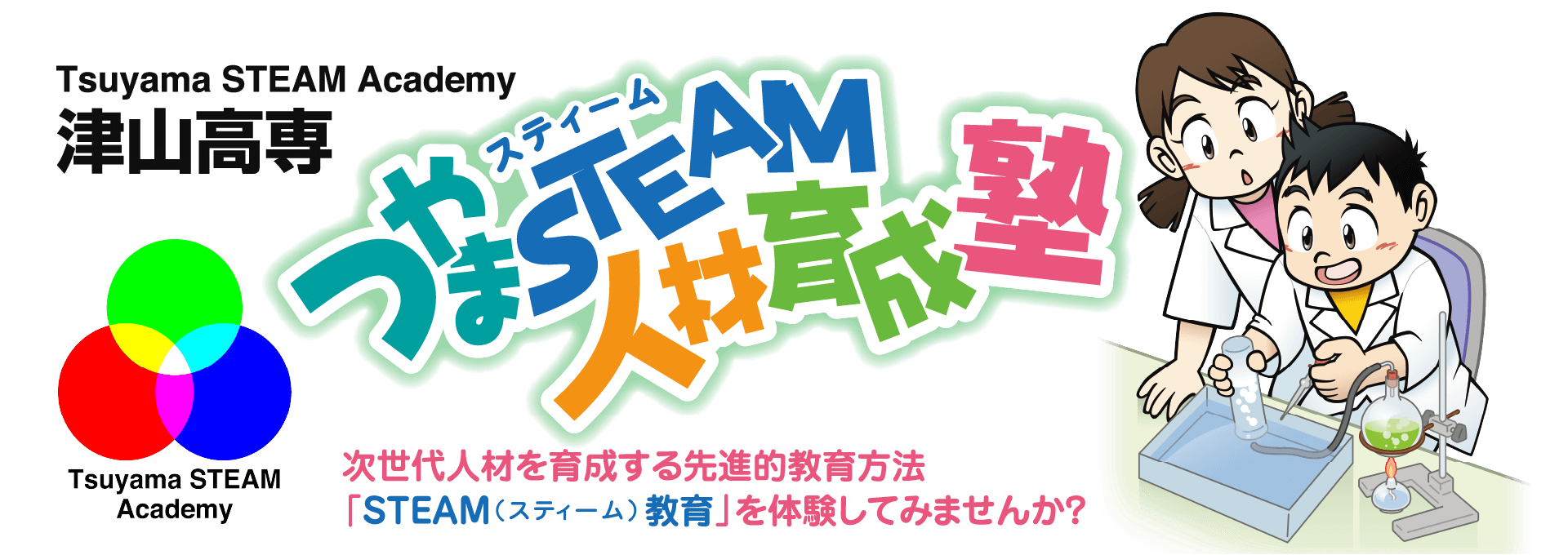活動報告
第11回目の講座を開催しました
2022.1.8 津山高専 マルチパーパス(ものづくり)
第11回目は、機械システム系の井上教授・加藤教授・専攻科2年生の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目)」を実施しました。「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第2回目となったこの日は、前回設計した竹とんぼの翼を3Dプリンタで印刷し、形状調整や塗装を行いました。
続けて、学生メンターの企画による教育プログラム「地球のエネルギーと環境問題~風力発電について考えてみよう!~」を実施しました。風を受ける方向による効率の違い等を模型を使って試してみました。
最後に、次回実施される探究活動発表会に向けて、発表の仕方、注意点などを学びました。
写真は、CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立ての講座の様子や、学生メンターによる風力発電の講座の様子です。


次回は1月22日(土)に「探究活動発表会」を開催します。
第10回目の講座を開催しました
2021.12.18 津山高専 情報演習室C・多目的ホール
第10回目は、機械システム系の西川准教授の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(1回目)」を学びました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第1回目となったこの日は、まず初めに3D-CAD設計ソフトであるSolid worksの操作を通して、ものづくりの基本的な仕組みや考え方を学び、続けて竹とんぼの設計を行いました。
続けて、情報システム系の寺元教授の指導で、「micro:bitプログラミング」を実施しました。
講座では、ハードウェアに内蔵されている各種センサーや、LED・スピーカーなどの出力装置について概要が説明されました。その後、Microsoft MakeCodeを用いたブロックプログラミングについて学習しました。最後にパソコンとマイコンボードを接続し、自作したプログラムでマイコンボード上のLEDを点灯させたり、スピーカーから効果音を鳴らしたりしました。
最後に、シニアメンターの吉富先生による探究活動では、1月に実施する探究活動発表会に向けて、発表の仕方や注意点などを学びました。
写真は、3D-CADで竹とんぼの設計をする受講生や、micro:bitプログラミングの講座のようすです。


次回は1月8日(土)に「CADCAM/3Dプリンタ/組立て2」の講座を開催します。
「第26回つやまロボットコンテスト」小中学生の部に本校ジュニアドクター育成塾チームが参加しました
2021.12.12 津山総合体育館
12月12日(日)に、津山総合体育館で「つやまロボットコンテスト」が開催され、本校ジュニアドクター育成塾の第2段階プログラム塾生による2チーム(各4名)が「小中学生の部」に出場しました。
今大会はフィールド内にあるボールを、ロボットを使って掃き出す「お掃除ロボコン」というテーマで、予選として2回の競技実演が行われ、得点合計上位4チームが決勝トーナメントへと選出される方式でした。
ジュニアドクターAチーム(写真1枚目)は、ほぼ満点のプレーができたものの、5番目の得点結果だったため決勝トーナメントには進出できませんでしたが、「アイデア賞」を受賞しました。
ジュニアドクターBチーム(写真2枚目)は、最初のプレー以外はパーフェクトゲームを繰り返し、予選は2位(同点2チーム)で決勝トーナメントに進出し、準決勝で惜敗したものの、最終順位は3位でした。


以上のように、昨年度・一昨年度に続き、今大会でも好成績を残すことができました。
第9回目の講座を開催しました
2021.12.4 津山高専 多目的ホール
第9回目は、電気電子システム系の西尾教授とその研究室の学生の指導の下で、「電子回路実験~無安定マルチバイブレータによるLED点滅~」講座で電子回路の基礎を学びました。
LEDをトランジスタとコンデンサで構成した無安定マルチバイブレータで点滅させる回路を組み、抵抗値や容量を取り換えて点滅時間の変化を確認しました。電子部品の働きを知ることで、次回の講座で学習するmicro:bitの内部の動作にも興味が沸いたと思います。
続けて、シニアメンターの吉富先生による探究活動では、各自行っている研究の進捗状況についてグループディスカッションを実施しました。
最後に、茨城高専佐藤誠先生を講師としてお招きし、「偏光板を使った実験」「逆シャボン玉」をテーマにワークショップを実施しました。色付きセロファンと回折格子を使って色と波長の関係を調べ、また、この光の性質を利用して、逆シャボン玉の観察を行いました。
これらを通して研究の進め方について学習しました。
写真は、電子回路実験を学ぶ受講生と、ワークショップのようすです。


次回は12月18日(土)に「CADCAM/3Dプリンタ/組立て1」の講座を開催します。
第8回目の講座を開催しました
2021.11.13 岡山県倉敷市
第8回目は、倉敷市の「ライフパーク倉敷科学センター」の見学に行きました。
中国地方最大級の規模をほこるプラネタリウムでは、当日の夜空の星座の探し方やおすすめ天文現象について学び、また、星や宇宙などさまざまな話題をテーマにした貴重な画像や迫力ある映像などを多用したショープログラム「プラネタリウムでチコちゃんに叱られる」を鑑賞しました。
また、科学展示室にはCGスクエアや国産技術で作られたロケットエンジンの実物などの展示が約100点設置されており、科学のおもしろさやすばらしさを体験することができました。
写真は、科学展示室の見学のようすです。


次回は12月4日(土)に「電子回路実験 ~無安定マルチバイブレータによるLED点滅~」の講座を開催します。