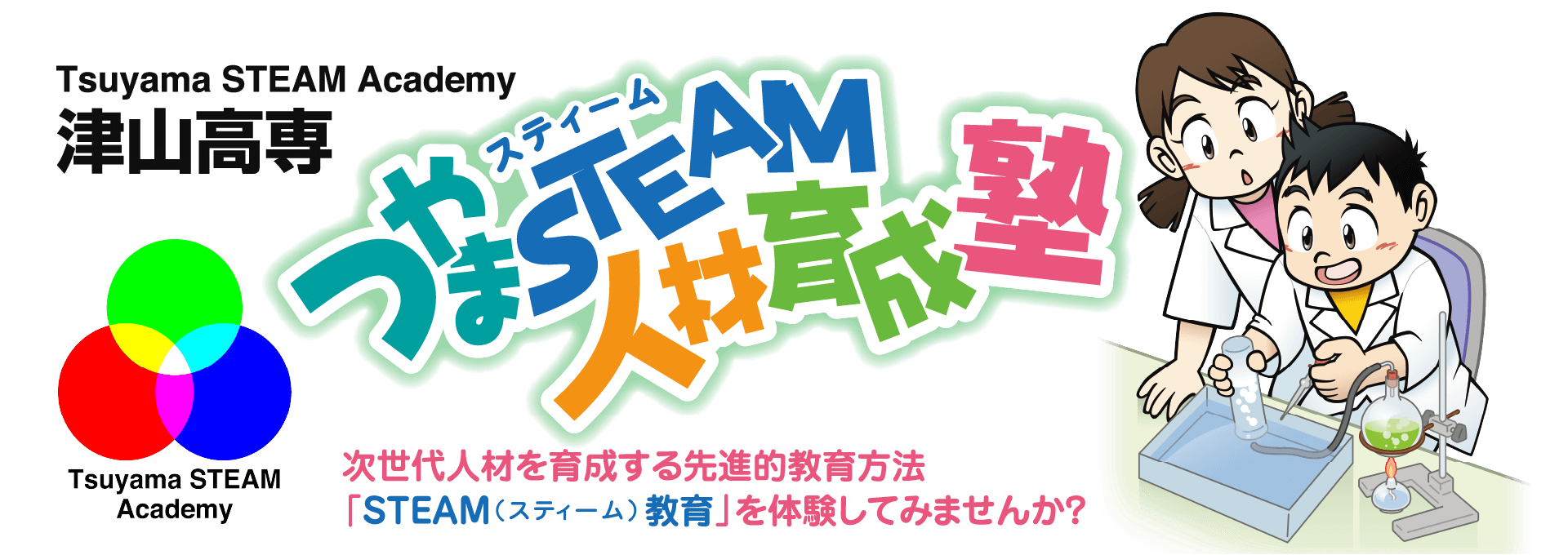活動報告
第二段階プログラム「研究発表会」・第一段階プログラム「探究活動発表会」を実施しました。
2025.2.14 津山高専多目的ホール/岡山サテライト教室(岡山県生涯学習センター)
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センター内に設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、この岡山サテライト教室と本校とをオンラインで結び、本校に通学すると同等の教育を展開しています。
今回は岡山サテライト教室と本校をオンラインで結び、発表会を実施しました。
午前中は第二段階プログラム研究発表会を実施しました。
第二段階プログラムでは在籍期間を原則2年間とし、各研究室に分かれて月1回程度のスクーリングまたはオンライン指導により研究を行っています。今回は1年目の受講生は中間発表、2年目の受講生は最終発表を行いました。
午後は第一段階プログラム探究活動発表会を実施しました。
発表会では、つやまSTEAM人材育成塾で学んだことをもとに各自が取り組んできた探究活動の成果をポスターにまとめ、発表を行いました。
受講生には約7ヶ月間の活動の中で科学分野の研究活動の流れを一通り体験していただきましたが、子供らしい素朴でユニークなテーマや取り組みの研究はいずれもレベルが高く、期待以上の成果を上げていました。
育成塾修了後も継続して取り組み、科学コンテスト等で発表していただけることを期待します。
写真は、第二段階研究発表会(津山会場)と第一段階探究活動発表会(津山会場)のようすです。


次回は3月7日(土)に第一段階・第二段階プログラム修了式を開催します。
第13回目の講座を開催しました
2026.1.10 津山高専マルチパーパス(生物)/マルチパーパス(ものづくり)
今回は、先進科学系の高木先生の指導で、生物実験「大腸菌から組換えタンパク質を取り出してみよう」の講座を実施しました。
まず、発光するオワンクラゲ由来のGFP「緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein)」遺伝子を組み込んだ大腸菌が発光することを実験で観察しました。
次に、超音波で大腸菌の細胞を破砕して洗浄・抽出を行い、得られたGFPに熱処理や酸処理を施して蛍光の有無を確認しました。
続けて、学生メンターの独自企画による教育プログラム「地球のエネルギーと環境問題~風力発電について考えてみよう!~」を実施しました。
再生可能エネルギーとして風力発電の仕組みを学び、風力発電小型模型キットを使って模型を組み立てました。受講生は羽根の形や角度を自分たちで工夫し、風車の形状ごとに発電量を比較しました。受講生どうしで話し合ったり、試行錯誤を通して羽根形状が発電効率に与える影響を観察し、科学的な思考力と協働学習の大切さを学びました。
写真は、生物実験と学生メンターの企画による教育プログラムのようすです。


次回は2月14日(土)に「探究活動発表会」を実施します。
第12回目の講座を開催しました
2025.12.20 津山高専多目的ホール/岡山サテライト教室(岡山県生涯学習センター)
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センターに設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、本校に通学すると同等の教育を展開していきます。
今回の講座は岡山サテライト教室と津山高専をオンラインで結び、メインテーマとして「理数系学びのジェンダーギャップの解消」と「津山洋学と国際情勢(蘭学者が見た世界)」の講演会を実施しました。
我が国には、女の子らしくとか、男の子らしくという古い概念が今もなお残っています。このようなバイアスが、女性の社会進出、特に科学や研究職へ進出の障害になっていることは否めません。小学生では理科や算数が好きな女子は多いが、中・高・大・大学院と進むにつれて理系女子はどんどん減っていく傾向にあります。
そこで、今回は、日本技術士会中国本部岡山県支部の支援を得て、女性技術者のロールモデルを招聘し、“ジェンダーギャップの解消”をねらいとして講演いただきました。最初に技術士制度について説明を受けた後、講師の女性技術士から、自分が目指してきたもの、やりがい、困難(ジェンダー関連)に対して対処対応したこと、現在の状況などについてお話いただきました。また、「ジェンダーギャップについて考えてみよう」・「自分のこと(将来の夢)について考えてみよう」のワークシートを使ってグループワークを行いました。受講生は、身近なジェンダーギャップや将来の夢について考え共有することで、自分の職業選択についてジェンダーフリーな意識を育むことができたと思われます。
続けて、津山洋学資料館から講師をお迎えし、グローバル教育の一環として、同館の企画展「蘭学者が見た世界」の内容をベースとして、「津山洋学と国際情勢(蘭学者が見た世界)」をテーマに講演いただきました。講演では、江戸時代末期から明治初期にかけての諸外国と日本の関係や、幕末の対外交渉で活躍した箕作阮甫の業績や、箕作省吾が刊行した日本初の世界地図である「新製輿地全図」(しんせいよちぜんず)についてお話いただきました。
最後に、情報システム系宮下先生(津山会場)・コーディネータの吉富先生(岡山サテライト教室)による探究活動指導として、2月に行われる「探究活動発表会」の発表方法や第二段階プログラムの募集要項について説明しました。
写真は、「理数系学びのジェンダーギャップの解消」と「津山洋学と国際情勢(蘭学者が見た世界)」の講演会のようすです。


次回は1月10日(土)に「生物実験」,「SDGSの講座(学生メンター独自企画)」を実施します。
「第30回つやまロボットコンテスト」につやまSTEAM人材育成塾チームが参加しました。
2025.12.14 津山市総合体育館
12月14日(日)に、津山総合体育館で「第30回つやまロボットコンテスト」が開催され、つやまSTEAM人材育成塾の第二段階プログラム塾生によるチーム(4名)が、「小中学生の部」に出場しました。
今大会は4チーム同時対戦型の競技テーマで、フィールドに置いてあるゴルフ練習ボールを回収し、フィールド中央のバスケットにゴールするような内容でした。
小中学生の部には24チームが参加しており、6チーム×4リーグに分けての予選が行われました。その後、準々決勝戦、準決勝戦および決勝戦が行なわれました。
1枚目の写真は本校Aチームの試合の様子で、ロボットハンドでボールを回収している様子です。
Aチームのロボットは安定した動作を繰り返し、最終的に決勝戦まで勝ち上がり、4位となりました。また、技術賞を受賞しました。

2枚目の写真は本校Bチームの試合の様子で、壁を利用してブルドーザのようにボールを回収している様子です。
Bチームのロボットは投石器を模した力強いシュートを何度も披露し、最終的に決勝戦まで勝ち上がり、準優勝しました。

末文となりましたが、大会参加に関してご支援、ご声援をいただきました保護者ならびに関係の皆様にお礼申し上げます。
第二段階プログラム受講生を対象としたグローバル教育(合宿研修)を実施しました
2025.12.6~7 津山高専国際寮
今回の合宿は、第二段階プログラムの受講生を対象に、受講生の国際感覚を養うことを目的に実施しました。
第1日目は、海外青年協力隊OVの中村哲也先生よりモンゴルの紹介があり、そしてそこからモンゴルと日本のトイレの比較、必要なトイレの機能についてディスカッションし、持続可能な社会建設に結びつけるという、ユニークな研修を受けました。
続いて津山高専のマレーシアの留学生がハラル食の説明をし、実際にみんなでハラルカレーを作り、食べてみるという体験をしました。初めてのハラルカレーでしたが、全員がおかわりをするという状況でした。さらにマレーシアのゲームを楽しむこともできました。
第2日は、津山高専の留学生による母国紹介と留学生面談です。
カンボジア、クロアチア、マレーシア、タイの4カ国の紹介プレゼンを聞いた後、留学生との個人面談となりました。大勢の中では発言しにくくても、一対一では話さざるを得ません。貴重な経験になったと思います。
写真は、中村哲也先生の研修のようすと、ハラールカレー作りのようすです。


1 / 2812345...1020...»最後 »