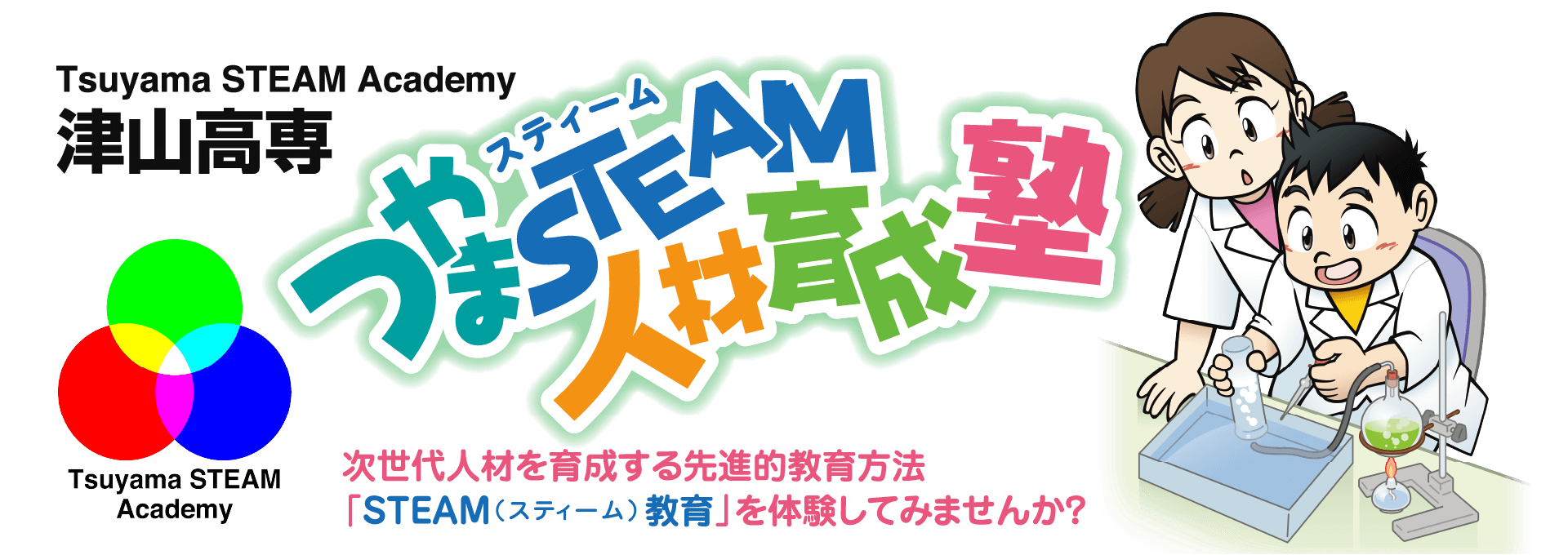活動報告
倉敷科学センター~青少年のための科学の祭典~に参加しました。
2019.11.9
第9回目は、倉敷科学センターで開催された「青少年のための科学の祭典」に参加しました。
午前中は、科学館展示の見学、プラネタリウムで秋の星座、はやぶさ2の活躍を学びました。
午後は、科学の祭典のブースを訪ね、様々な分野の科学体験・工作に挑戦しました。電子レンジで小麦粉粘土、液晶で虹色のアクセサリー、UVレジンで光るアクセサリー、火山降下物の標本作りなど、興味深いブースが展開されていました。
参加した受講生には、科学の祭典の中で印象深かった題材をひとつ選んでレポートをまとめることが課されています。
写真は、科学センター玄関での朝の集合の様子とUVレジンアクセサリーのブースで製作に取り組む子供たちの様子です。

次回は11月30日(土)に「奥出雲たたらと刀剣館」・「奥出雲多根自然博物館」を訪問します。
第8回目の講座を開催しました
2019.10.26 津山高専 図書館・総合情報センター2F 多目的ホール
第8回目は、電気電子システム系の西尾教授と研究室の学生の指導の下で、電子回路の基礎を学びました。
LEDをトランジスタとコンデンサで構成した無安定マルチバイブレータで点滅させる回路を組み、抵抗値や容量を取り換えて点滅時間の変化を確認しました。
電子部品のはたらきを知ることで,前回の授業で用いたmicro:bitの内部の動作にも興味が深まったと思います。
後半は、前回課題の宿題をもとに研究者倫理の復習をグループ討論で行いました。また、不思議体験では、自励振動を利用した玩具を工作しました。ばねの太さや長さ、おもりを変えて振動落下の様子を確認しました。
写真は、LED点滅回路を組み立てている様子と自励振動玩具を作っている様子です。

次回は11月9日(土)に「倉敷科学センター~青少年のための科学の祭典~」に参加します。
第7回目の講座を開催しました
2019.10.19 津山高専 図書館・総合情報センター2F 情報演習室A・多目的ホール
第7回目は、先進科学系の佐藤誠教授の指導で、micro:bitのプログラミング(2回目)を学びました。
まず初めに、前回の宿題になっていたmicro:bitで方位磁石を作る「電子コンパス」のプレゼンを各グループの代表者が行いました。
続けて、前回の講座では、micro:bitに組み込まれたセンサーの数値を読み込み、内蔵されたLEDを表示させることを学びましたが、今回はさらに、外部接続したLEDや角度制御サーボモーターと連続回転サーボモータのPWM制御を学びました。
後半の、シニアメンターの吉富先生の指導による「研究者倫理を理解しよう」&「探求企画書を書いてみよう(前半)」の講座では、研究論文不正に陥らないためのルールや心構え・注意すべきことや、実験・観察結果を実験ノートに記録する重要性等について学びました。
写真は、micro:bitのプログラミングを学ぶ受講生のようすと深化学習のようすです。

次回は10月26日(土)に 電気回路実験~無安定マルチバイブレータによるLED点滅~についての講座を開催します。
美作サイエンスフェアに参加しました。
2019.9.28 美作大学
9月28日(土)の6回目のジュニアドクター育成塾は、美作大学で開催された科学実験イベント「美作サイエンスフェア」に参加しました。
「美作サイエンスフェア」では美作地域の高専、高校等から16件の実験・工作ブースが出展され、受講生たちはそれぞれ興味のあるテーマに参加しました。内容は、生物、化学、地学、物理分野など広範にわたり、子どもたちの関心を集めるように工夫されており、参加した受講生の満足度も高いものとなりました。
写真は、津山高専から出展した、佐藤教授による「作って飛ばそう!紙コプター!」と廣木准教授による「光と化学の実験室」のようすです。

次回は10月12日(土)にmicro:bitプログラミング についての講座(2回目)を開催します。
第5回目の講座を開催しました
2019.9.14 津山高専 図書館・総合情報センター2F 情報演習室A・多目的ホール
第5回目は、電気電子システム工学科の桶真一郎准教授の指導でmicro:bitのプログラミングを学びました。プログラム通りにセンサーの入力をもとにLEDを点灯させることができると、受講生は驚きと達成感を感じているようでした。次回までにmicro:bitで方位磁石を作る課題が出されました。どのような作品を作ってくれるか楽しみです。
後半は,探求テーマの調べ報告とテコの原理のワークショップをシニアメンターの吉富先生の指導で行いました。5gのおもりと三角クリップだけで30cm物差しの質量を求める課題に取り組みました。
写真は、micro:bitのプログラミングを学ぶ受講生のようすと深化学習のようすです。

次回は9月28日(土)に行われる美作サイエンスフェアに参加します。