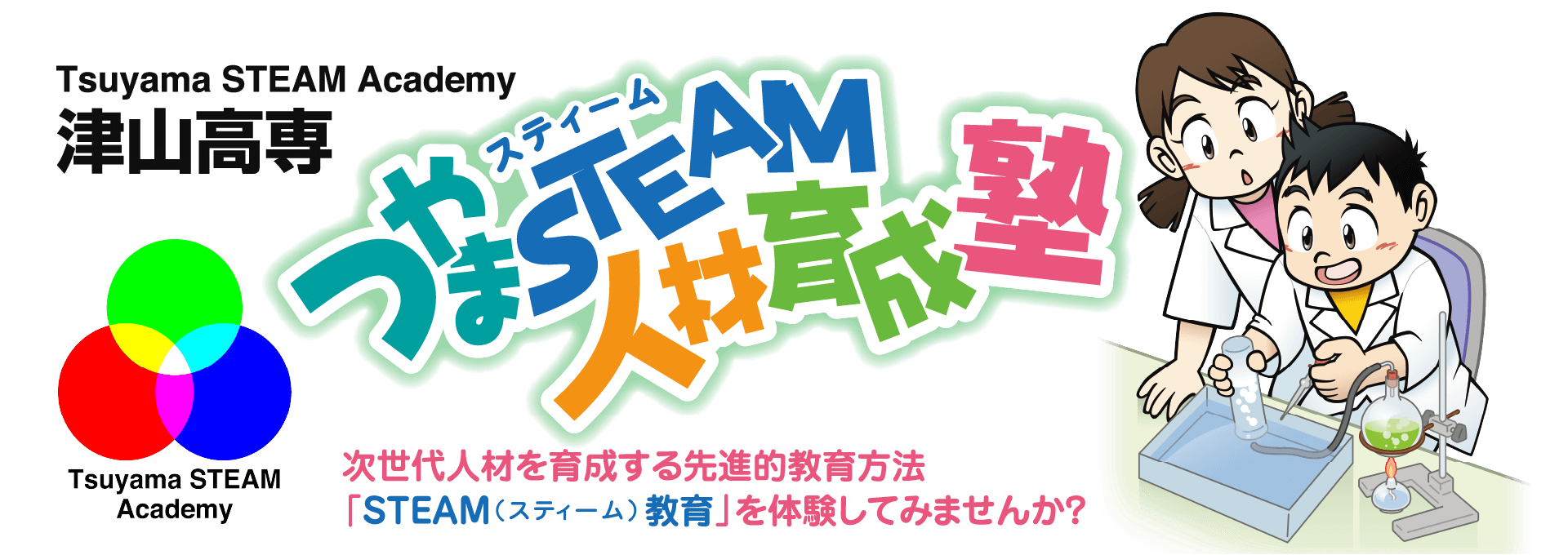活動報告
第二段階受講生がサイエンスカンファレンスで特別賞・分野賞を受賞しました
2019.11.16-11.17
11月16日と17日にお台場テレコムセンターにて開催されたサイエンスアゴラのプログラムのひとつとして全国のジュニアドクター育成塾実施機関が集うサイエンスカンファレンスが実施されました。
初日は、受講生のポスター発表、2日目はスタディツアーに参加し、受講生間の友好を深め、また実施機関担当者間で情報交換を行いました。
本校塾からは第二段階受講生の長谷川隼平さんと江見心さんが参加し、ポスター発表では、長谷川さんは「マクラギヤスデの生態の探究」で特別賞を受賞、江見さんは「Stand up!wake up!マイクロビット電子工作」で情報・工学融合分野賞を受賞しました。
長谷川さん、江見さんおめでとうございます!
第12回目の講座を開催しました
2019.12.21 津山高専 物理実験室
第12回目は、機械システム系の井上教授・加藤准教授の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目)」を実施しました。
このプログラムでは、計3回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる印刷、コンテストで学習結果の確認を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第2回目となったこの日は、前回設計した竹とんぼの翼を3Dプリンタで印刷し、形状調整や塗装を行いました。
後半は、先進科学系・佐藤先生の,探求活動を発表するための「ポスターの書き方の基本を知ろう」の講義を受けました。ポスターの雛形に自分の研究内容を書きこんでいく方法を学びました。
続けて、シニアメンターの吉富先生の指導によるワークショップで,「消える妖精」の不思議な数理を学びました。
写真は、竹とんぼの翼の形状調整等をおこなっている受講生のようすと、「消える妖精」のワークショップのようすです。

次回は1月11日(土)に「 CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(3回目) 」についての講座を開催します。
第11回目の講座を開催しました
2019.12.14 津山高専 図書館・総合情報センター2F 情報演習室C・多目的ホール
第11回目は、機械システム系の趙准教授・西川講師の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(1回目)」を学びました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計3回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる印刷、コンテストで学習結果の確認を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第1回目となったこの日は、まず初めに3D-CAD設計ソフトであるSolid worksの操作を通して、ものづくりの際の基本的な仕組みや考え方を学び、続けてSolid worksで竹とんぼの設計を行いました。
後半は、シニアメンターの吉富先生の指導による「探求企画書を書いてみよう(後半)&ワークショップ/コイルモーター」の講座を行いました。「探求企画書を書いてみよう(後半)」では、前回の宿題の「探求企画書を書いてみよう」について、各自が書いてきた内容をグループ内で発表して、他者の企画を参考にするとともに相互に意見交換するというグループワークを行いました。
「ワークショップ/コイルモーター」では、“コイルモーター”を題材に、電気と磁気の作用でエナメル線の輪が回り続ける原理等について学びました。
写真は、竹とんぼの設計をしている受講生のようすと深化学習のようすです。

次回は12月21日(土)に「 CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目) 」についての講座を開催します。
第10回目の講座を開催しました
2019.11.30
第10回目は、島根県の「奥出雲たたらと刀剣館」と「奥出雲多根自然博物館」の見学に行きました。
午前中は「奥出雲たたらと刀剣館」で、日本刀の原料になる玉鋼を生産するための古代からの製鉄法「たたら製鉄」について学びました。実物大のたたら炉断面模型やたたら吹きで使われた吹子の実物模型など、いにしえのたたら操業の一部を体験しました。
午後は「奥出雲多根自然博物館」を訪問しました。ここでは約40億年におよぶ貴重な化石が多数展示されており、地球の進化と生命の歴史を学ぶことができました。
写真は、「奥出雲たたらと刀剣館」の吹子の体験と、「奥出雲多根自然博物館」でティラノサウルスの見学のようすです。

次回は12月14日(土)にCADCAM/3Dプリンタ/組み立てについての講座を開催します。
11月16日、17日にジュニアドクター育成塾サイエンスカンファレンスが開催されました
2019.11.16-11.17
11月16日と17日にお台場テレコムセンターにて開催されたサイエンスアゴラのプログラムのひとつとして全国のジュニアドクター育成塾実施機関が集うサイエンスカンファレンスが実施されました。
初日は、受講生のポスター発表、2日目はスタディツアーに参加し、受講生間の友好を深め、また実施機関担当者間で情報交換を行いました。
本校塾の第二段階受講生2名が参加し、micro:bitの電子工作とヤスデの研究を報告し、それぞれ情報・工学融合分野賞と特別賞を受賞しました。
写真は、ポスター発表の様子とサイエンスアゴラでのステージ発表の様子です。