第二段階修了式を実施しました。
3月17日(金)に、今年度末で中学校を卒業する第二段階プログラムの受講生を対象に、修了式を実施しました。
当日は11名の修了生のうち、9名が参加しました。
修了式では、岩佐校長よりそれぞれ修了証書が手渡され、激励の言葉が贈られました。
写真は修了証書を受け取る受講生の様子です。


高校生になっても継続して研究に取り組み、輝かしい実績を積んでいけるよう、受講生の皆さんの活躍に期待しています。
本プロジェクトは国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)の「次世代科学技術チャレンジプログラム」事業に採択され、実施しております。
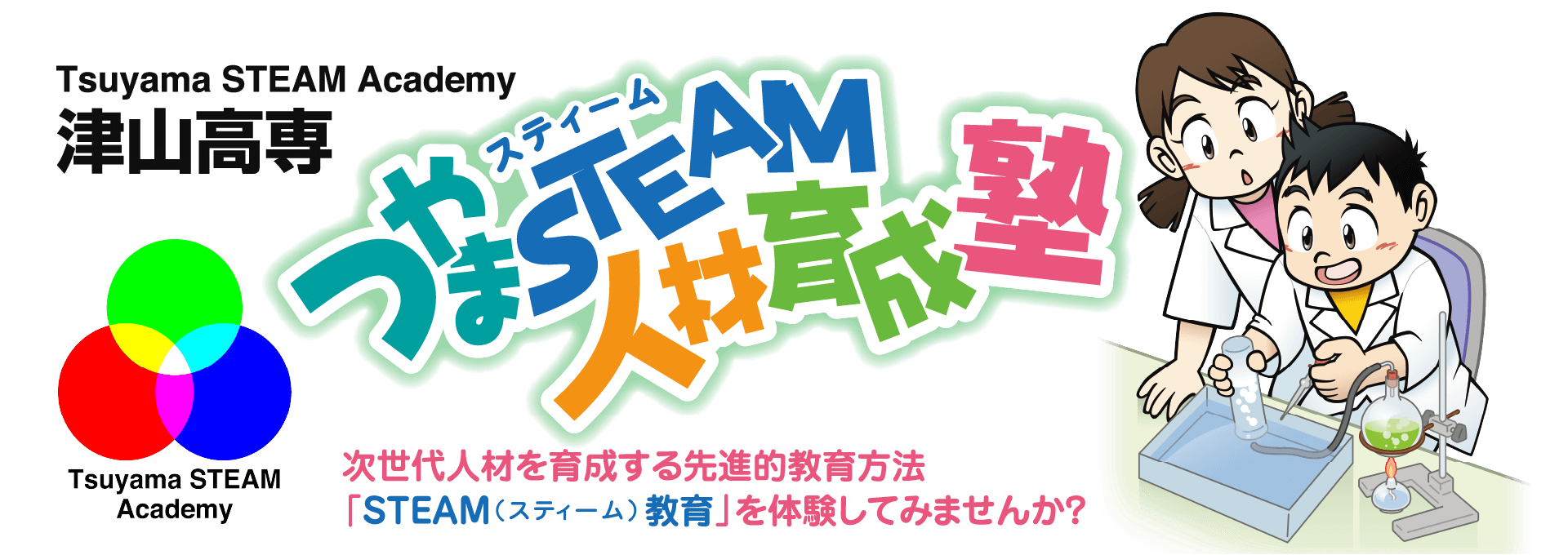
3月17日(金)に、今年度末で中学校を卒業する第二段階プログラムの受講生を対象に、修了式を実施しました。
当日は11名の修了生のうち、9名が参加しました。
修了式では、岩佐校長よりそれぞれ修了証書が手渡され、激励の言葉が贈られました。
写真は修了証書を受け取る受講生の様子です。


高校生になっても継続して研究に取り組み、輝かしい実績を積んでいけるよう、受講生の皆さんの活躍に期待しています。
2023.2.4 津山高専 多目的ホール
第13回目は今年度最後の活動です。
この日は修了式・探究活動ポスター表彰式を実施しました。
修了式では、岩佐校長先生より激励の言葉が贈られ、受講生の代表者に修了証が手渡されました。
また、受講生自らがテーマを設定し、その解決に向けて実験・観察・調査を行った結果をまとめた「探究活動ポスター」の表彰式を実施しました。
最優秀賞や優秀賞、物理学賞、化学賞、生物学賞、チャレンジ賞、審査員特別賞等、計13名の受講生が賞を受賞しました。


今後は受講生の中から数名を選抜し、個別の研究活動を支援する第二段階プログラムへ継続していただく予定です。
5期生のみなさんには、育成塾修了後も継続して取り組み、科学コンテスト等で発表していただけることを期待しています。
2023.1.14 津山高専 マルチパーパス(ものづくり)
第11回目は、機械システム系の井上教授・加藤教授・専攻科1年生の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目)」を実施しました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第2回目となったこの日は、“よく飛ぶ竹とんぼ”について、その角度や必要な力などについての講義を行い、続けて、前回の講座で設計し、3Dプリンタで印刷した竹とんぼの翼の形状調整や塗装を行いました。
続けて、学生メンターの企画による教育プログラム「地球のエネルギーと環境問題~風力発電について考えてみよう!~」を実施しました。風を受ける方向による効率の違い等を模型を使って試してみました。
最後に、次回実施される探究活動発表会に向けて、発表の仕方、注意点などを学びました。
写真は、竹とんぼの翼の形状調整と、学生メンターの企画による教育プログラムの講座のようすです。


次回は1月28日(土)に探究活動発表会を開催します。
2022.12.3 津山高専 情報演習室C・多目的ホール
第10回目は、機械システム系の西川准教授と山田准教授の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(1回目)」を学びました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第1回目となったこの日は、まず初めに3D-CAD設計ソフトであるSolid worksの操作を通して、ものづくりの基本的な仕組みや考え方を学び、続けて竹とんぼの設計を行いました。
続けて、シニアメンターの吉富先生による探究活動では、第二段階プログラムの内容説明および選抜方法について説明しました。
また、ワークショップでは、自励振動現象の楽しさや恐ろしさを学んだ後、自励振動を利用した理科玩具(キツツキ)を工作しました。工作では、ばねの太さや長さ、おもりを変えて振動現象の様子を確認しました。
写真は、3D-CADで竹とんぼの設計をする受講生や、ワークショップのようすです。


次回は1月14日(土)に「CADCAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目)」の講座を開催します。
2022.12.11 津山総合体育館
12月11日(日)に、津山総合体育館で「つやまロボットコンテスト」が開催され、本校ジュニアドクター育成塾の第2段階プログラム塾生による2チーム(各3名)が、「小中学生の部」に出場しました。
今大会は、赤色と青色のプラカップを貼り合わせた「アイテム」を用いての陣取り合戦がテーマで、予選として2回の競技実演が行われ、得点合計上位4チームが決勝トーナメントへと選出される方式でした。
ジュニアドクターAチームは予選Cリーグに出場しましたが、アイテムをつかむことに苦労し、残念ながら0勝1敗1分けでした。
写真(左)がAチームの試合中の様子で、フィールド上のアイテムをつかもうとしているところです。
ジュニアドクターBチームは予選Bリーグに出場し、2勝0敗0分けでしたが、惜しくも得失点差で決勝トーナメントに進出することはできませんでした。
写真(右)がBチームの試合中の様子で、つかんでいるアイテムをスポットへ運んでいるところです。
この後、アイテムをひっくり返しながらスポットに差し込むことで得点を重ね、勝利をしました。
この機構が評価されたのか、幸いなことに、アイデア賞を受賞しました。


以上のように、今大会でも好成績を残すことができました。