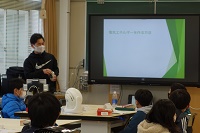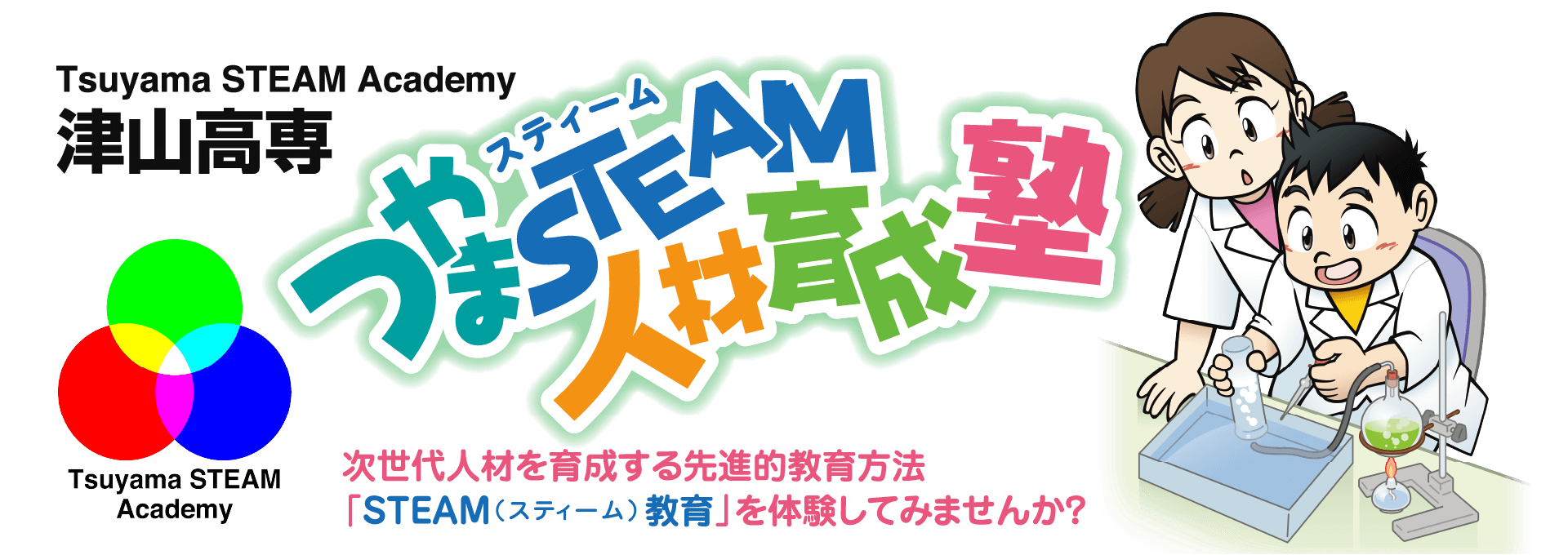活動報告
第9回目の講座を開催しました
2021.1.9 津山高専 物理実験室
第9回目は、機械システム系の井上教授・加藤准教授の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(2回目)」を実施しました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第2回目となったこの日は、前回設計した竹とんぼの翼を3Dプリンタで印刷し、形状調整や塗装を行いました。
続けて、学生メンターの企画による教育プログラム「地球のエネルギーと環境問題~風力発電について考えてみよう!~」を実施しました。風を受ける羽の形状や枚数による効率の違いを模型を使って試してみました。
また、先進科学系・佐藤先生のワークショップでは、11月に見学した「和鋼博物館」のたたら製鉄を再現する実験を試みました。電子レンジ内でテルミット反応を起こし、砂鉄をアルミニウムで還元して玉鋼を作りました。
最後に、次回実施される探究活動発表会に向けて、発表の仕方、注意点などを学びました。
写真は、竹とんぼの形状調整をするようすと学生メンターの企画による教育プログラムのようすです。

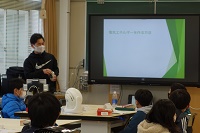
次回は1月23日(土)に探求活動発表会を実施します。
第8回目の講座を開催しました
2020.12.19 津山高専 情報演習室C・多目的ホール・総合理工学科南館南側広場
第8回目は、機械システム系の趙准教授・西川講師の指導で、「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て(1回目)」を学びました。
「CAD・CAM/3Dプリンタ/組み立て」では、計2回の講座を通して、3D-CADを用いた竹とんぼの設計、3Dプリンタによる造形、最後に学習内容のレポート提出を行い、設計から製作までの流れを学習します。
第1回目となったこの日は、まず初めに3D-CAD設計ソフトであるSolid worksの操作を通して、ものづくりの基本的な仕組みや考え方を学び、続けて竹とんぼの設計を行いました。
後半の深化学習では、先進科学系の佐藤教授の指導で、塾生が取り組んできた探究活動をまとめるためのポスター制作について学びました。
また、当日、屋外で、かつて中国地方で栄えた古代製鉄法の「たたら製鉄」の公開実験がつやまたたらの会主宰で行われており、炭と砂鉄を原料に身の回りにある道具を利用して鉄(和鋼)つくりを再現する様子を見学しました。塾生は、先月島根県安来市にある和鋼博物館を訪問して「たたら製鉄」について学んでおり、今回の公開実験の見学で、たたら製鉄についての知識を深めることができました。
写真は、3D-CADで竹とんぼの設計をするようすとたたら製鉄見学のようすです。


次回は1月9日(土)にCADCAM/3Dプリンタ/組み立て2回目(全2回)の講座を実施します。
第7回目の講座を開催しました
2020.12.12 津山高専 第1共通実験室・多目的ホール
第7回目は、電気電子システム系の西尾教授とその研究室の学生の指導の下で、二足歩行ロボット制御プログラミングを学びました。
まずは、ロボットの基本的な動作をさせることによって、その機構を動作させる面白さを経験。続けてプログラミングを実施し、ロボットの動作確認をすることで、プログラムの役割を学習しました。さらに、オリジナルな動作のプログラミングを行い、ロボットの動作を確認しました。
これらを通して、アクチュエータ、センサと制御回路の関係を学ぶことができました。
また、シニアメンターの吉富先生のワークショップでは、モーターなどの駆動装置や特別な制御装置を必要としない歩行形態である受動的動歩行をする“受動歩行ロボット(トコトコ人形)”を製作しました。
この製作により、ロボット歩行の基礎として静歩行と動歩行があることや、制御方法として、アクティブ制御(能動制御)とパッシブ制御(受動制御)があることを理解しました。
写真は、二足歩行ロボット制御プログラミングを学ぶ受講生と、受動走行ロボットの講座のようすです。


次回は12月19日(土)にCADCAM/3Dプリンタ/組み立て1回目(全2回)の講座を実施します。
「第25回つやまロボットコンテスト」小中学生の部に本校ジュニアドクター育成塾チームが参加しました
2020.12.13 津山市久米総合文化運動公園体育館
12月13日(日)に、久米総合文化運動公園体育館にて「第25回つやまロボットコンテスト」が開催されました。新型コロナウイルス対策として、今回は参加チーム数が制限されておりましたが、ジュニアドクターAチームならびに近隣小中学校の合計12チームが小中学生の部に参加しました。
今年のテーマは「狙え!ダンク!(?)バスケットボールロボコン」で、各チームは1台のロボットを製作し、バスケットボールを模した競技ルールで対戦を行い、時間内での得点を競いました。真ん中の写真は競技中の様子で、ジュニアドクターAチームのロボットがボールをキープしながら運んでいるところです。
チームメンバーの応援を受けながら、操縦者(右の写真の黒いマスクの選手)がロボット操作を頑張りました。予選では津山東中学校チームと北陵中学校チームと対戦しましたが0対0で引き分け、その後のジャンケン勝負で2位となり、惜しくも決勝進出はできませんでした。
ジュニアドクターAチームのロボットはデザイン賞を受賞し、昨年度に続き好成績を残すことができました。



たたらの総合博物館「和鋼博物館」の見学に行きました。
2020/11/28
第6回目は、島根県安来市にある「和鋼博物館」の見学に行きました。
「和鋼博物館」では、日本の伝統的製鉄法の「たたら」を再現して炎を燃やし、製鉄の様子が体感できる展示室や、鉄ができるまでの工程を解説する映像のほか、国の重要有形民俗文化財にも指定、明治時代に作られたという送風装置「天秤ふいご」などの実際に使われていた製鉄用具の展示などを通じ、江戸時代から明治にかけ中国山地で盛んに行われていた製鉄について学びました。
写真は、館内の見学と「天秤ふいご」の体験のようすです。


次回は12月12日(土)に二足歩行ロボットプログラミングについての講座 を開催します。