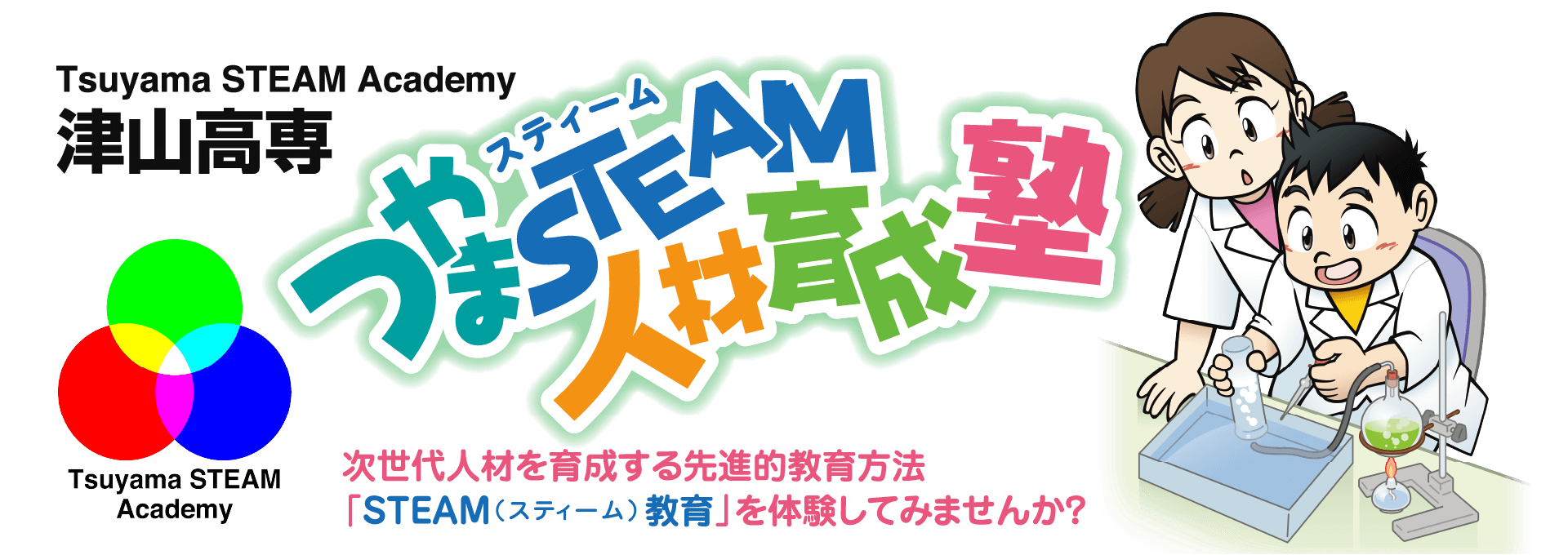活動報告
プレイベント「科学実験体験教室」を開催しました
2024.5.25 津山高専 総合理工学科南館
5月25日(土)に、つやまSTEAM人材育成塾プレイベント「科学実験体験教室」を開催しました。
「つやまSTEAM人材育成塾」は、文部科学省の関係機関である国立研究開発法人科学技術振興機構の「次世代科学技術チャレンジプログラム」に採択され、津山高専が実施している次世代人材育成プログラムです。小学5年生から中学3年生の段階において、科学技術に対する強い興味がある児童生徒を対象に、STEAM教育の考え方を取り入れて、その能力の更なる伸長を図る体系的な育成プログラムとなっています。
現在第2期生を募集していますが、事業に関心をお持ちの方を対象にプレイベントを実施し、小中学生と保護者の約102名が参加しました。
プレイベントでは「ドローン操縦体験~自動操縦ドローンと競争しよう!~」や「micro:bitで遊ぼう!」など、計8個の体験ブースを出展しました。物理・生物・化学の各実験室を見学する「ラボツアー」では、3Dプリンター、顕微鏡を使った生物実験、化学実験などを体験していただきました。
また、第二段階受講生による研究発表をまとめたポスター展示も行いました。参加者は思い思いのイベントに参加し、熱心に取り組んでいました。


第一段階・第二段階プログラム修了式を開催しました。
2024.3.16 津山高専多目的ホール
今年度最後の活動となったこの日は、第一段階・第二段階修了式、第一段階探究活動ポスター表彰式を実施しました。
修了式では、実施主担当者の宮下先生より激励の言葉が贈られ、受講生の代表者に修了証が手渡されました。
また、第一段階の受講生自らがテーマを設定し、その解決に向けて実験・観察・調査を行った結果をまとめた「探究活動ポスター」の表彰式を実施しました。最優秀賞や優秀賞、物理学賞、化学賞、生物学賞、チャレンジ賞、審査員特別賞等、計16名の受講生が賞を受賞しました。
写真は、第一段階探究活動ポスター表彰式と第二段階修了証授与式のようすです。


修了式の後は、ロボコン指導教員の宮下先生が、今年度第二段階プログラムロボコンチームが出場し準優勝を獲得した「つやまロボコン」についての紹介をしました。続けて、コーディネータの吉富先生の指導によるワークショップで、「消える妖精」の不思議な数理を学びました。
今後は第一段階の受講生の中から数名を選抜し、個別の研究活動を支援する第二段階プログラムへ継続していただく予定です。
修了生のみなさんには、育成塾修了後も継続して取り組み、科学コンテスト等で発表していただけることを期待しています。
第9回目の講座(探究活動発表会)を実施しました。
2024.3.2 津山高専多目的ホール
第9回目の講座は「探究活動発表会」を実施しました。
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センター内に設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、この岡山サテライト教室と本校とをオンラインで結び、本校に通学すると同等の教育を展開しています。
今回は岡山サテライト教室と本校をオンラインで結び、発表会を実施しました。
発表会では、つやまSTEAM人材育成塾で学んだことをもとに各自が取り組んできた探究活動の成果をポスターにまとめ、発表を行いました。
受講生には約4ヶ月間の活動の中で科学分野の研究活動の流れを一通り体験していただきましたが、子供らしい素朴でユニークなテーマや取り組みの研究はいずれもレベルが高く、期待以上の成果を上げていました。
育成塾修了後も継続して取り組み、科学コンテスト等で発表していただけることを期待します。
写真は、津山高専会場と岡山サテライト教室の発表のようすです。


次回は3月16日(土)に第一段階・第二段階プログラム修了式を開催します。
第8回目の講座を開催しました
2024.2.17 津山高専多目的ホール
第8回目は、機械システム系の関先生の指導で、「古代製鉄方法から学ぶ現代製鉄の基礎講座」というテーマのもと、岡山県を含む中国地方を中心に日本独自に発展してきた製鉄技術である“たたら製鉄”について学びました。
たたら製鉄とは主に砂鉄と木炭のみを用いて鉄塊をつくる方法で、日本刀の素材となる玉鋼(たまはがね)などはこの製鉄法のみで生産されます。講座では、その製造方法や鉄の還元にかかわる原子の動き(化学反応)、現代製鉄と古代製鉄の製造方法の違いや特徴について学びました。
続けて、機械システム系の塩田先生とその研究室の学生の指導の下で、「ペーパーブリッジ講座」を実施しました。
軽くて強いペーパーブリッジを作るために、まずは板の曲げの強度や変形抵抗について、いろいろなサンプルの実験を進めながら測定しました。次に、その知識をもとに、薄い紙を使って強く変形しにくいブリッジの製作を行いました。
最後に、情報システム系の宮下先生の指導で、「研究倫理」の講座を実施しました。研究論文不正に陥らないためのルールや心構え・注意すべきことや、実験・観察結果を実験ノートに記録する重要性等について学びました。
写真は、「古代製鉄方法から学ぶ現代製鉄の基礎」と「ペーパーブリッジ講座」のようすです。


次回は3月2日(土)に「探究活動発表会」を開催します。
第7回目の講座を開催しました
2024.2.3 津山高専多目的ホール/岡山サテライト教室(岡山県生涯学習センター)
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センター内に設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、この岡山サテライト教室と本校とをオンラインで結び、本校に通学すると同等の教育を展開しています。
今回は岡山サテライト教室と本校をオンラインで結び、講座を実施しました。
まずは、サブコーディネータの杉山先生による「グローバル教育2/留学生と交流(互いの国・文化の紹介)」を実施しました。
モンゴル、マレーシア、タイ、インドネシアから来ている本校の留学生が母国の文化や習慣等について紹介し、次に受講生のグループの中に入り、グループごとに交流しました。受講生は、気候や食べ物、好きなアニメ、将来の夢等について積極的に質問し、他国を知る貴重な経験となりました。また、アメリカ、ヨーロッパに偏りがちな視点を、東アジアや東南アジアにも向ける機会にもなりました。
続けて、情報システム系の宮下先生による探究活動を実施しました。
受講生が個々にテーマを設定して取り組んでいる探究活動について、そのポスターのまとめ方を説明し、また、受講生がグループに分かれて研究の進捗状況についてグループディスカッションを実施しました。
写真は、グローバル教育 津山会場と岡山サテライト教室のようすです。


次回は2月17日(土)に「古代製鉄方法から学ぶ現代製鉄の基礎」・「ペーパーブリッジ講座」を開催します。