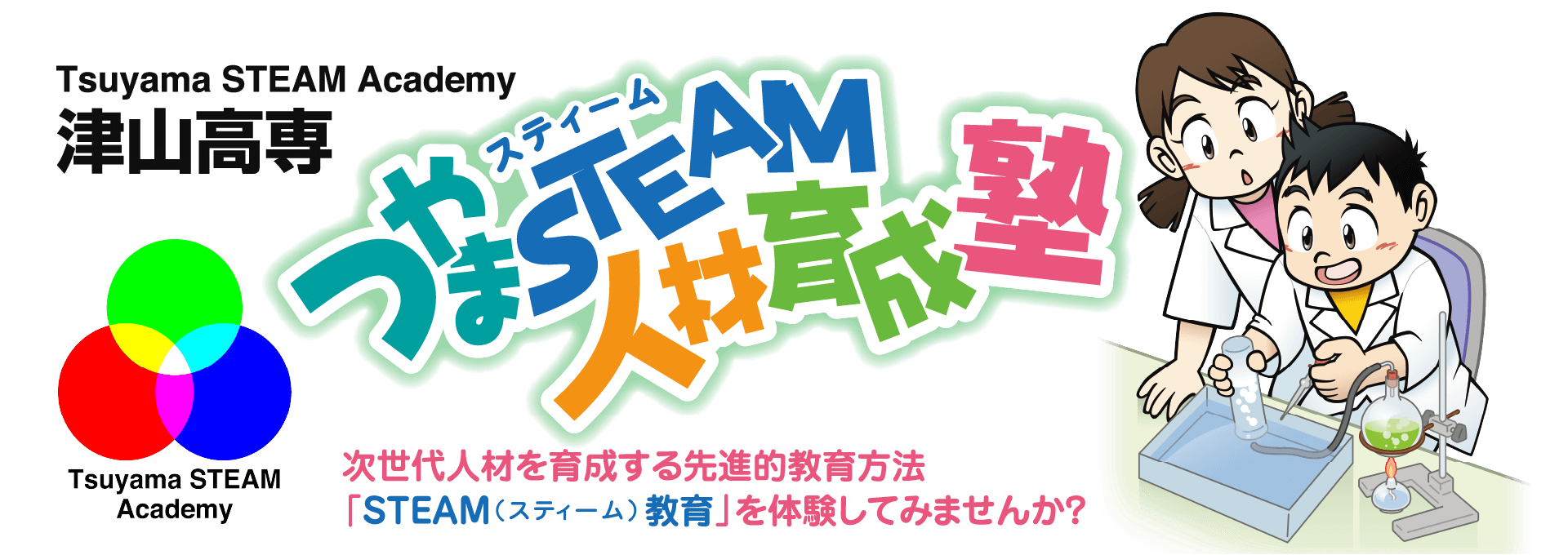活動報告
第7回目の講座を開催しました
2025.10.11 津山高専化学実験室・合併教室
今回は、先進科学系の廣木先生とその研究室の学生の指導で、「津山洋学/舎密開宗(せいみかいそう)の再現実験」、電気電子システム系の中村(直)先生の指導で、「情報リテラシー」講座、美作大学の渡邊先生の指導で、「備前焼事前学習」を行いました。
本校のある津山市を中心とする美作地方(岡山県北東部)は、江戸時代から明治初期にかけて、日本の近代化に貢献した優秀な洋学者(蘭学者)を輩出しています。
「津山洋学/舎密開宗(せいみかいそう)の再現実験」では、江戸時代の津山藩医である宇田川榕菴(ようあん)が編著訳された日本初の本格的な化学実験書「舎密開宗(せいみかいそう)」について、そこに記された江戸時代の化学、そして現代にそれがいかに影響したかを再現実験と観察をとおして体感しました。
情報リテラシー講座では、研究活動を行う際のモラルとして、情報を扱うコンピュータやインターネットを利用するときに注意するポイントとなる“著作権”や“情報の信ぴょう性”について学びました。
備前焼の事前学習では、日本の「やきもの」の歴史や、備前市伊部周辺で備前焼が隆盛したことの地理的背景などを学びました。また、釉薬(ゆうやく)を一切使わない備前焼にヒダスキなどの美しい窯変が現れる理由を酸化焼成や還元焼成の化学反応の面から学びました。
写真は、情報リテラシー講座と、舎密開宗の再現実験のようすです。


次回は9月13日(土)に岡山県倉敷市「大原美術館」・「ライフパーク倉敷科学センター」を訪問します。
第6回目の講座を開催しました
2025.9.27 津山高専多目的ホール/岡山サテライト教室(岡山県生涯学習センター)
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センター内に設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、本校に通学すると同等の教育を展開していきます。
津山高専会場では、機械システム系の塩田先生とその研究室の学生の指導の下で、「ペーパーブリッジ講座」を実施しました。
軽くて強いペーパーブリッジを作るために、まずは板の曲げの強度や変形抵抗について、小学生は模型を使った実験で、また、中学生は電卓を使って測定しました。次に、その知識をもとに、薄い紙を使って強く変形しにくいブリッジの製作を行い、その上に乾電池を置いて強度を確認しました。
岡山サテライト教室では、電気電子システム系の中村(直)先生の指導で、2足歩行ロボット制御プログラミングを学びました。
まずは、ロボットの基本的な動作をさせることによって、その機構を動作させる面白さを経験しました。続けてプログラミングを行い、ロボットの動作確認をすることで、プログラムの役割を学習しました。さらに、オリジナルな動作のプログラミングを行い、ロボットの動作を確認しました。これらを通して、アクチュエータ、センサと制御回路の関係を学ぶことができました。
続けて先進科学系の谷口先生(津山高専会場)、コーディネータの吉富先生(岡山サテライト教室)による「探究活動」を実施しました。
受講生がグループに分かれ、各々が設定した探究テーマや実験・観察・調査の方法、スケジュール等を発表しました。
写真は、ペーパーブリッジ講座(津山高専会場)と、探究活動(岡山サテライト教室)のようすです。


次回は10月11日(土)に「津山洋学の講座/舎密開宗の再現実験」・「情報リテラシー講座」を実施します。
「大原美術館(対話型アート鑑賞)」・「ライフパーク倉敷科学センター」の見学に行きました。
2025.9.13 岡山県倉敷市 大原美術館・ライフパーク倉敷科学センター
9月13日(土)に、第一段階プログラムの小中学生35名が、倉敷市の大原美術館およびライフパーク倉敷科学センターを訪問しました。
大原美術館では、ただ鑑賞するだけではなく、一つの視覚教材をみんなで囲み“見る・考える・話す・聴く”という対話型アート鑑賞を行いました。同じ絵に対しても様々な視点があり、一緒に見学していた教員にとっても新たな発見のある経験でした。
ライフパーク倉敷科学センターでは約100点の展示物を有する科学展示室での体験と、プラネタリウムを鑑賞しました。科学展示室では受講生は各自で興味のある展示を回り、関心を深めたようです。
写真は、大原美術館とライフパーク倉敷科学センターの見学のようすです。


次回は9月27日(土)に「ペーパーブリッジ講座(津山高専会場)」・「二足歩行ロボット講座(岡山サテライト教室)」を開催します。
第4回目の講座を開催しました
2025.8.9 津山高専合併教室/岡山サテライト教室(岡山県生涯学習センター)
本企画では、広く受講機会を供与するため県南地域の受講希望者を対象とした「岡山サテライト教室」を岡山県生涯学習センター内に設置して受講生が協働して学ぶ場を確保し、本校に通学すると同等の教育を展開していきます。
今回は岡山サテライト教室と本校をオンラインで結び、講座を実施しました。
まずは、受講生のモチベーションアップを目的とし、2018年度ジュニアドクター育成塾(第一期)の修了生2名による「修了生講演」を実施しました。
2名はジュニアドクター育成塾修了後本校へ進学し、現在先進科学系5年と機械システム系4年に在籍しています。講演では、育成塾を受講しようと思った動機、本校の授業の特長、部活動、留学経験や将来の夢等について講演しました。
続けて、機械システム系の関先生の指導で、「古代製鉄方法から学ぶ現代製鉄の基礎講座」というテーマのもと、岡山県を含む中国地方を中心に日本独自に発展してきた製鉄技術である“たたら製鉄”について学びました。
たたら製鉄とは主に砂鉄と木炭のみを用いて鉄塊をつくる方法で、日本刀の素材となる玉鋼(たまはがね)などはこの製鉄法のみで生産されます。講座では、その製造方法や鉄の還元にかかわる原子の動き(化学反応)、現代製鉄と古代製鉄の製造方法の違いや特徴について学びました。
最後に、情報システム系の宮下先生(津山高専会場)、コーディネータの吉富先生(岡山サテライト教室)による「探究活動」の講座を実施しました。
各々が研究テーマを決めて取り組んでいく探究活動について、前回の講座で配布した企画書を使って進捗確認等を行いました。
写真は、修了生講演と、古代製鉄方法から学ぶ現代製鉄の基礎講座(津山高専会場)のようすです。


次回は10月25日(土)に「津田永忠の史跡をめぐる(田原井堰・田原用水水路橋・閑谷学校見学)」を実施します。
たたらの総合博物館「和鋼博物館」の見学に行きました。
2025.8.2 島根県安来市 和鋼博物館
第3回目は、日本の伝統的製鉄法の「たたら」に関する日本で唯一の総合博物館である「和鋼博物館(島根県安来市)」の見学に行きました。
「和鋼博物館」では、日本の伝統的製鉄法の「たたら」を再現して炎を燃やし、製鉄の様子が体感できる展示室や、鉄ができるまでの工程を解説する映像のほか、国の重要有形民俗文化財にも指定、明治時代に作られたという送風装置「天秤ふいご」などの実際に使われていた製鉄用具の展示などを通じ、江戸時代から明治にかけ中国山地で盛んに行われていた製鉄について学びました。
また、『砂鉄を知ろう!~鉄穴流しの模型で大実験~』というワークショップでは、鉄穴流し模型を使い、砂鉄と土砂の比重の違いを利用して土砂の中から砂鉄のみを取り出し集める体験をしました。この体験を通して、たたら製鉄の材料集めのために行っていた鉄穴流しには、科学的な原理があったことがわかりました。
写真は、館内の見学とワークショップのようすです。
(写真は和鋼博物館の許可を得て掲載しております。)


次回は8月9日(土)に「修了生講演」・「古代たたら製鉄の講義」を開催します。